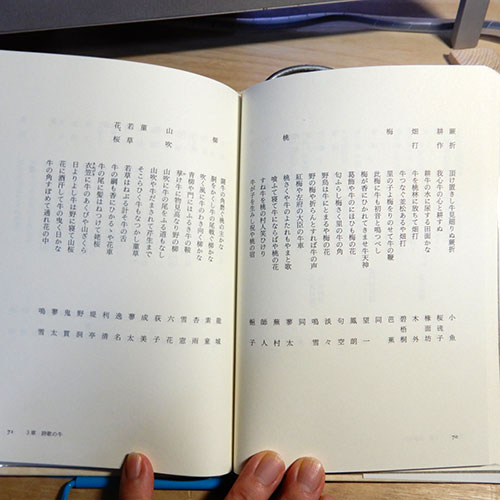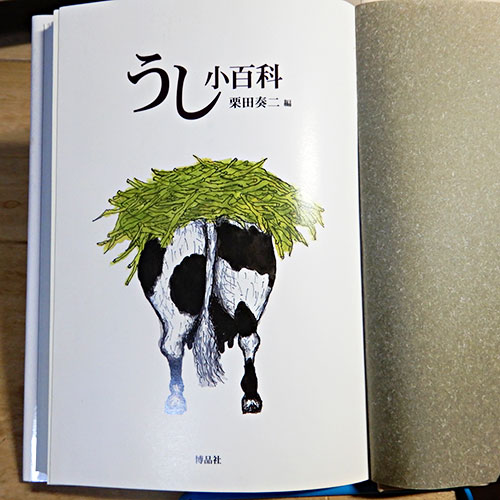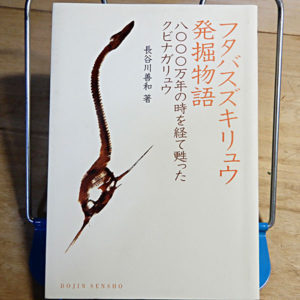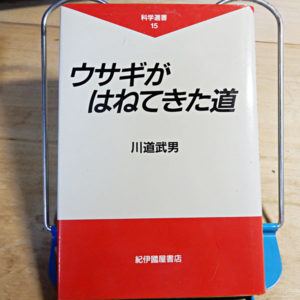栗田奏二『うし小百科』
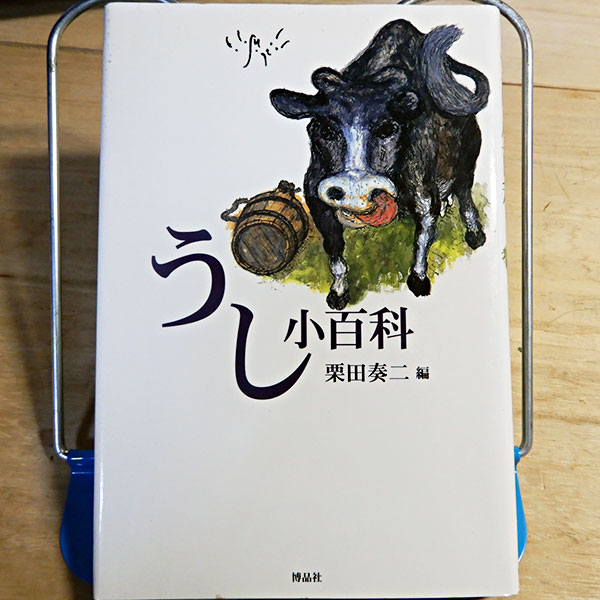
ウシのこと、皆さん、どれほどご存知ですか?
平成21年(2009年)、明けましておめでとう!
今年は丑年。ってわけで、牛の本のご紹介。(注:書評掲載時)
現代日本人で、牛のお世話になっていない人なんて皆無だろう。
ナニ、「自分はビンボーで牛肉のステーキなんて何年も食ってないぞ」ですって?
私だって“ステーキ”は何年も食べていません。「菜食主義者」ですから。
だけど昔は牛乳大好き、アイスクリームも好き、バターやチーズも使う。牛にはお世話になりっぱなしだった。またこの間のクリスマスディナーは“ビーフシチュー”だったし。いえ、入れた素材は、タマネギ、人参、大根と大根葉、サツマイモ、ブロッコリー、油揚げにニョッキ(すいとんとも言う)・・・、と、ここまでは菜食だけど、味付けに使ったのが市販の“ビーフシチュールウ”。ルウには当然(多分?)牛肉エキスも入っている。牛さん、ごめんなさい。
牛は、間違いなく、人類の繁栄を支えた大黒柱の一つだと思う。
我々人類がどれほど牛を使い、牛に頼り、牛に支えられて生きてきたか。多分「人類の最大の友」犬が存在しなかったとしても、人類はそれなりに発展できただろうが、もしこの世に牛が存在しなかったら、文明の発展はおそろしく遅延させられたに違いない。あるいは全く発展できなかったかもしれないとすら思う。
牛が提供してくれたのは、肉や乳だけでない。古代においては牛はまさに「モーター」だった。牛の力を借りて、古代人類は地面を耕した。農業を支えたのは牛だった。牛の力を借りて、古代人類は重い物を運搬した。交易を支えたのも牛だった。牛の毛皮や皮を使って、人類は靴や入れ物や、馬に付ける鞍まで作った。生きている間は乳を貰い、死ねばその肉を食った。まさに牛様々である。
その牛について、多くの現代人はあまりに無知だ。「恩知らず」と言われても仕方がないほどに。
この本は、そんな不甲斐ない我々現代人のために、牛と人のかかわりをみっちり説いてくれた本だ。牛のありがたさを思い出させてくれる本だ。
それだけでない。牛が出てくる漢詩や故事など、一般教養も高めてくれる。牛にまつわる神話伝説、牛にちなんで付けられた動植物の名、牛の諺、その他その他。牛がどれほど身近で大切な存在であったか、あらためて思い知らされる思いだ。
今年は丑年。
12年前の丑年に出版されたこの本を、是非ご一読の上、あらためて牛さんに感謝の意を表されるべし。
(2009.1.1.)
※著作権法に配慮し、本の中見の画像はあえてボカシをいれております。ご了承ください。
『うし小百科』
- 著:栗田奏二(くりた そうじ)
- 出版社:博品社
- 発行:1996年
- NDC:645(家畜各論・犬、猫)
- ISBN:4938706334 9784938706333
- 171ページ
- 登場ニャン物:-
- 登場動物:ウシたち
目次(抜粋)
1章 牛の歴史
一、牛をめぐる言語と分類
二、牛の期限
三、牛の概念-東西文明の違い
四、日本・朝鮮と牛
五、日本の現在の牛種
2章 神話伝説
一、牛は女性の象徴
二、自然伝説の牛
三、自然神話の牛
四、物語ものの牛
3章 詩歌の牛
4章 禅と十牛
5章 故事俚諺
6章 牛にちなむ雑話
7章 牛拾遺
8章 牛にちなむ動物と植物
補遺
編者の言葉