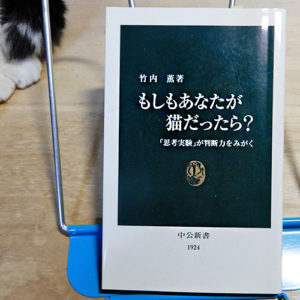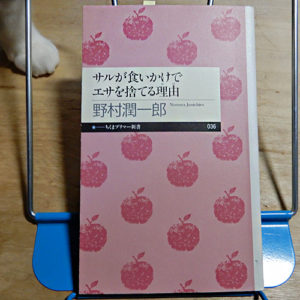香山リカ『イヌネコにしか心を開けない人たち』

マスコミでも人気の精神科医による本。
著者は精神科医。
幼少時代から、家の中には常にペットがいた。そして今もイヌ1匹ネコ5匹と暮らしている。
ひどいペットロスに苦しんだこともある。精神科医として、他人の心のケアはプロのはずなのに、その時、自分の心はどうしようもなかったという。
その著者にして、
「最近、世間のペットブームもやや行きすぎではないか、と感じる場面が多い。」
そうだ。
390万円の室内兼用ベッド。 犬用おせちに、犬用ひな祭りマフィンセット。
徳島市の“がけっぷち犬”救出騒動を、テレビで繰り返し放映。世界にはもっと重大な出来事が起こっているはずなのに。
著者はイルカによるアニマル・アシステッド・セラピーに参加してみたこともある。 物心付く前からペットと一緒に暮らして来た著者は、ペットがどれほど愛しい存在か、よく分かる。 どれほど慰められるかも、よく分かる。
にもかかわらず、心のどこかでなんか変だぞと思っている自分がいる。
ペットを溺愛し、溺愛していることを隠そうともしない大人たち。
著者によると、3つのタイプに分類できるという。
「愛情の対象がないから仕方なくペットに」
「愛情の対象がいるのにそちらを放置してペットに」
「愛情の対象をあえて求めることもなく、最初から自然にペットに」。
第一のタイプは、たとえば配偶者に先立たれたり子供が独立したりで、こういう人は
「機会さえあればペット以外の人間を愛する力もあるのだから、周囲が適切な人間関係を再構築する援助をすることが必要であろう。」
と書く。
第二のタイプについても、
「『本末転倒』があまりにひどくなった場合は、やはり誰かが何らかの手を差し伸べたり忠告してあげたりする必要があるだろう。」
第三のタイプは、新しいタイプで、
「誰も犠牲にしたり迷惑をかけたりしておらず、また『家族がいない』『結婚できない』といった何かの代償にペットを飼っているわけでもない」
「仕事をこなして経済的にも自立しているのだから、その点でも批判はしにくい。」
しかし著者によれば、一番問題なタイプだという。 ペットは人間より短命だ、死亡した場合どうするのか、と。
それから話は動物愛護活動についての考察にうつる。
インターネットでの里親募集ボランティアが、たとえば交通費まで負担して里親希望者の自宅に犬猫を届けることについて
「ちょっと尋常でない熱意」
を感じてしまう著者。
そして、ボランティアたちと一般人の間に生じやすい温度差の原因を
「心に余裕がないから動物愛護に走る」
ためだと指摘する。
「心に穴が開いた人、傷ついた人が集まって保護活動が行われているとするなら、そこでさまざまな人間関係のトラブルが起きるのも十分、予想できることではある。」
「その背景にある最も大きな問題は、活動をする人の多くが、生活や心に余裕があるから動物にもそのエネルギーを向けたり、人間にもやさしい人がそのやさしさを動物にも向けたりしているのではなく、逆に満たされない心を動物、もしくは動物愛護の活動で埋めようとしている、というところにあるのではないだろうか。」
そういう面も、たしかにあるだろう。
しかし、それは動物愛護活動に限ったことではないと思うのだ。
なんらかの理念を掲げて活動している人というのは、たいてい、どこか満たされない部分があるからこそ、活動するのじゃないだろうか。
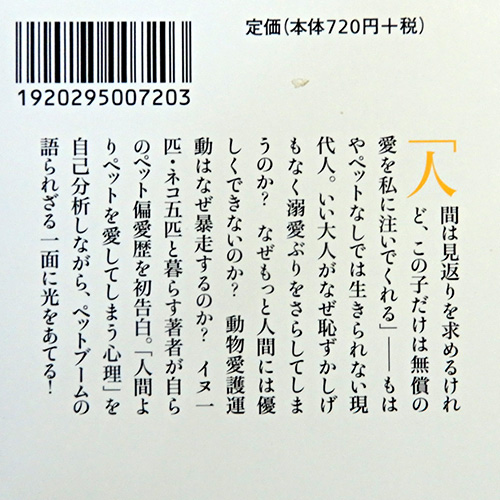
香山リカ『イヌネコにしか心を開けない人たち』
私は、動物愛護団体をふくめ、およそボランティア団体というものは、宗教団体みたいなものだと思っている。
そしてしかし、宗教が愛を説き慈悲を説いていながら、宗派が違うだけでたちまち戦争にまで発展しちゃうのが “悲しき人間のサガ” ってもの。
動物愛護団体だけが美しくピュアだなんて、妄想もよいところだ。 宗教にせよ、その他どんな思想的活動にせよ、悟りの境地にまで達せられる人は少ないものだ。
とはいえ、現状に何の疑いも持たない、よどんだ水たまりのような人間よりは、理想を求めて動く人のほうを、私は評価したい。
それに、「動物好きに悪人はいない」とまでいくとウソになるが、「猫好きに悪人は少ない」程度ならかなり本当じゃないかと思う。 下手な宗教より、一匹の子猫の方が、人を救う能力は高いのではないかとも。
それから、これは悲しいことだが、どれほど人間好きだった人でも、ひとたび野良猫救済活動をはじめると、どんどん人間嫌いになっていく傾向がある。壮絶な虐めにあうからだ。その虐めがどれほど陰険で陰湿かは、実際に体験した者でないと想像もつかないだろう。他人の所有物は決して盗まない善人が、他人が可愛がっている猫を虐待して平気なのである。虐待の理由は「目障りだ」。
私に言わせれば、心が傷ついた人が保護活動に走るのではなく、保護活動をした結果として、心がボロボロに傷つけられるのである。傷つけられても活動を止めないだけの意志の強さを持った人たちだけが活動家として残るのであれば、保護活動家は全員心に傷を持った人間だという指摘は正しい。
ところで。
私が猫を里親様宅まで届ける第一の理由は、それが生き物だからだ。
生きている以上、ポストに投入するわけににはいかない。安全に譲渡するには、譲る方もしくは譲られる方のいずれかが、自ら運搬するしかない。
さて、その猫を保護したのは私の勝手である。 さらに、好きで保護したにもかかわらず、里親様という他人にあとを托すのも私の勝手である。
猫は10年以上生きるのが普通になってきた。 20年生きる子も珍しくない。その間にかかる手間もコストも相当なものだ。
里親募集するということは、届けるまでは私が責任をもつけれど、あとは餌代砂代動物病院代、掃除も看病も何もかも、すべてそちらでよろしくねっていう、かなり勝手な話だと私は解釈している。
だから自分で連れて行くのだし、その交通費を請求するなんて考えないのである。
しかし、猫ボランティアを続けている人の多くが経済的に大変なのも事実だ。 費用に関しては当事者間で決めれば良いことだと思う。 里親側が望むなら、その猫にかかった費用すべてを払えばよい。 本当の愛猫家ボランティアなら、もらったお金は次の猫保護費にまわすだろう。
また。
この本では、少子化とペット溺愛の関係についても書かれている。
少子化がペットブームを呼んだのか、むしろペット溺愛が少子化の原因のひとつとなっているのか。
著者によれば、子どもふたりまでが、ペット溺愛の分水嶺だそうだ。
著者は精神科医として、あくまで「人と人との関係」の中でだけ記述されているので、私は無謀にもあえて全然別な角度から、私なりのド素人考えを書いてみたいと思う。
ヒトは動物の一種である。 動物は、その地域における生息数が増えすぎると、それ以上繁殖をしなくなるという性質を持つ。 繁殖できなくなると言うべきかもしれない。 個が繁殖しなくなることで種の絶滅を防ぐしくみだ。
ヒトには他の動物には無い情報収集力がある。 想像力もきわめて豊かだ。 そして日本には様々な情報がかなり自由にはいってくる。
世界人口がどれほどの勢いで増え続けているか、そして人間活動が地球にどんな影響を与えているか。 日本人なら誰でも知っている。
他の様々な要因にプラスして、この人口爆発にたいする生物的恐怖心が、ホモ・サピエンスの頭脳に、繁殖欲を押さえ込ませる要因のひとつとして働いていやしないか?
もし働いていたとしても、多分それを個々人が意識することはないだろうとは思う。 っていうか、いくら人間が想像力豊かだとしても、世界人口の爆発と我が子を産むこととを結びつけて繁殖を断念するなんてことがあるだろうか? かなり疑問ではある。
とはいえ・・・
「これ以上世界人口が増えたらやばいよなあ」
という気持ちは、日本人なら誰でも持っていると思うのだ。
くわえて、現実世界での、子育ての大変さ。 産む気が萎えたとして不思議はない。
しかしヒトという動物は、愛し育む対象無しにはいられない心理構造を持っている。 ヒトの子は他の生物に類を見ないほど育てるのが難しいから、ヒトは他の生物に類を見ないほど強い愛着心を我が子に対して持つよう本能付けられているのだ。
結果、生物の本能で繁殖を止め、ヒトの本能でペットを愛すようになった。
・・・なんてね。飛躍しすぎ?いや、そうは思えないのだが。
(2008.5.6.)
*上記書評を書いたあと、「地球を救うには子供の数を減らせ」というまじめな論文を見つけた。
Scientists: Save the planet-have fewer kids
(By Laurie Goering ; Chicago Tribune correspondent 2:17 AM CDT, August 27, 2008)
やはりどう考えても、世界的に少子化をすすめ世界人口を減らすことが地球を救う最良かつ唯一の道のように思えてならない。
(2008.8.29.追記)
※著作権法に配慮し、本の中見の画像はあえてボカシをいれております。ご了承ください。
『イヌネコにしか心を開けない人たち』
- 著:香山リカ(かやま りか)
- 出版社:幻冬舎新書
- 発行:2008年
- NDC:645.6(家畜各論・犬、猫)
- ISBN:9784344980693
- 189ページ
- 登場ニャン物:-
- 登場動物:-
目次(抜粋)
第1章 戸惑いのペットブーム
第2章 医者も頼りにするペット
第3章 私のペット偏愛歴
第4章 メロメロ知識人が増える理由
第5章 ペット愛の新しいかたち
第6章 暴走する「動物愛護」
第7章 ペットロスは理性を超えて
第8章 なぜイヌやネコでなければダメなのか
あとがき