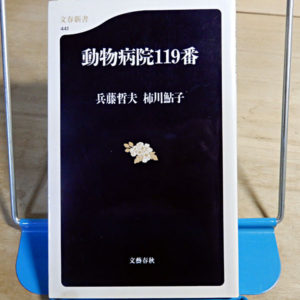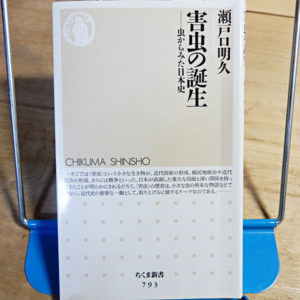東ゆみこ『猫はなぜ絞首台に登ったか』
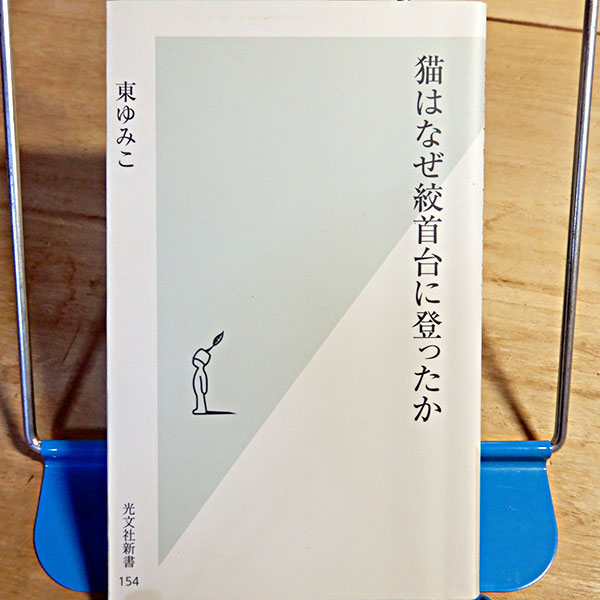
かつて、ヨーロッパでは、動物が人同様に裁判にかけられていた。
残虐なタイトルの本だが、内容はおどろおどろしいオカルトではない。現代神話学の本である。
この本では、十八世紀中葉のヨーロッパの事例を中心として、神話そのものはもちろんのこと、生活の中で普段は気づくことのない神話の力についても、考えてみようと思っています。現代人にとっての神話を明らかにすることで、私たちが生きる上で、無意識に依拠しているものは何なのか、とらえなおしてみたいのです。
(p.7)
さて、18世紀半ばのヨーロッパでは、動物虐待がいたるところで横行していた。
たとえば、ロンドン。ウィリアム・ホガースという画家が1751年頃に描いた「残酷の四段階」という四枚続きの版画。その中には猫、犬、馬、羊、その他が虐待されている様子が描かれている。
次に、1730年パリで起こった事件。とある印刷工場で、職人達が猫を集め、裁判にかけた挙げ句、猫たちを全員絞首刑にしてしまった。しかもその光景を見て大爆笑したという。
今の日本人の我々には、感覚として理解できない。なぜそんな残虐なこと平気でできるのか?一人二人の人間がやったことなら個人的な精神的異常として片付けられるけれど、大勢の人間が平然と、時には笑い飛ばしながら、猫や動物たちを逆さづりにして殺すなど残虐な行為を繰り返している。
動物を裁判にかけるとなると、ますます理解できない。単なる“裁判ごっこ”ではない。『正式な手続きに乗っ取り、検察側、弁護側の答弁がきちんと行われました。目撃者に話しを聞いたり、法律家にも意見を訪ねたりします。』というのだ。
このような動物裁判は、特にフランスで頻繁にみられたものでした。いまだ発見されていない史料の存在の可能性と、何をもって動物裁判とするのかという研究者の判断の違いから、正確な数字は判明していないようです。ある学者は十二世紀から十八世紀のフランスで九十五例あったと主張し、別の学者によれば、フランスのロレーヌ地方だけで二十五例見いだせると言います。
(p.135)
著者はその心理を色々な方面から説いていく。
産業革命により出現した「大都市」と階級闘争。
カーニヴァルや四旬節の伝統。
ヨーロッパ人にとって「絞首刑」のもつ意味。
タロットカードや「死と再生」。
ギリシア神話、等々。
・・・と、文面では理解できても、現代日本人の私にはやはり、心情的には全然理解出来ないというのが正直な感想である。
(2008.9.20.)
※著作権法に配慮し、本の中見の画像はあえてボカシをいれております。ご了承ください。
『猫はなぜ絞首台に登ったか』
- 著:東ゆみこ(ひがし ゆみこ)
- 出版社:光文社新書
- 発行:2004年
- NDC:230(ヨーロッパ史、西洋史)
- ISBN:9784334032548
- 214ページ
- 登場ニャン物:
- 登場動物:
目次(抜粋)
第1章 十八世紀、猥雑のロンドン
第2章 コンタは見た―印刷工たちのパリ
第3章 都市の詩学
第4章 この世は笑う
第5章 絞首刑のアーケオロジー
第6章 穀物霊と神話の力