今野保『羆吼ゆる山』

羆を身近に感じながら暮らしてきた男。
近年、クマ騒動が毎年のように繰り返されている。
クマ(たいていは大人しいツキノワグマ)が、人里に出て人間にチラリとでも目撃されるや否や、たちまち警察やら猟友会やらテレビカメラやらに追いかけられ、追い詰められ、包囲され、射殺されてしまう。
年間数百頭単位で射殺駆除されているのである。
その一方で、「熊さんかわいそう」と騒ぐ人々もいる。都会の公園のどんぐりを集めて山に運び熊さんに食べてもらおうとか、殺駆除した村役場にメールや電話攻撃をかけるとか。
そういう運動は、私にも、気持ちとしてはすごく理解できるのだけれども、しかし、なんとなく、なんというか・・・
せっせとドングリを集めて送っている人たちが、もし山村に住んでいて、もし自分の畑や庭の柿の木が、クマに荒らされたらどう反応するんだろうかと思うと・・・それでもクマの味方をしてくれるのだろうか?
(実は私もそういう環境に住んでいる。犬の散歩に熊撃退スプレーを持ち歩く毎日なのである。でも、だからこそ、私は「クマたちの味方だ」と堂々と胸を張って言えると自負もしている。)
人とクマの共存は、本当に難しい問題だ。
『羆吼ゆる山』の著者は、1917年北海道生まれ。山の中の、ヒグマ生息地の真っただ中で人生の多くを過ごされた方だ。
本は著者の、小学校2年生の想い出からはじまる。
小学校2年生といえば、7~8歳だと思うが、そんな幼い子供が、片道5kmの山道を、淋しく、険しく、時にはヒグマも出る山道を、子供たちだけで、時には子供一人で、歩いて通学していたという事実が、まず、現代の都会人には驚きを通り越して、非現実とすら感じられるのではないだろうか。
その子供は、ある日、ひとりで帰宅途中、山に入っていくおじさんの黒い背中を見かけた。
いくら慣れている道とはいえ、まだ小2、一人歩きは心細い。
大人がいるのなら、ぜひ一緒に歩いてほしいのが本音だ。
「おじさーん、どこへ行くのー。・・・」
子供は大声で呼びかける。
「あ、あんなところにいた。今、行くから待ってよ」
と声をかけ、路肩に一歩足を踏みだした瞬間、いきなりガバッと後ろから自分を抱え上げたものがあった。びっくりして声も出せず固く目を閉じたままの私を抱えたものは、そのまま道なりに走っているようであった。・・・
(p.20)
いきなりドキッとさせられる出だしである。
この子供は食べられちゃったんだろうか、いや、こうして本を出しているのだから無事だったはずだ、それにしてもなんて際どい!
こうして、著者はヒグマと密接にかかわっていく。
といってもヒグマ専門の猟師ではない。
本職は炭焼きや炭鉱。
しかし食を得るため身を守るために、鉄砲も撃つ。
たまたまそこにヒグマが出た場合には、ヒグマをも撃つ、という立場である。
それだけにかえって、生活に密接した、生々しいクマ体験が綴られる。
クマ猟師なら、わざわざクマを探して歩くのだから、クマと出会って当然である。
著者達はクマをむしろ避けているのに、クマの方からやってきて家の周りに出没する。
襲われてはたまらない。
近所の男たちと銃を持って立ち向かうことになる。
あるいは。
畑の横で、囲炉裏端で、クマ撃ち名人の話に聞き入る。
獰猛なヒグマとの一騎打ちに心躍らせ、マタギの知識に感嘆する。
すごい生活だなあと思う。
けれども、ある意味で、古き良き時代だったなあとも思う。
ヒグマは日本列島に生存する、もっとも強大な肉食獣である。
どれほど猛獣であろうと、共存が困難であろうと、それでも私はやはり、ヒグマとヒトとは永久に共存してほしいのである。
「解説」を書かれた宮原昭夫氏も、同じ思いらしい。
それにしても、この本に出てくるヒグマたちは、どこか悲しい。(中略)なんだか何時の間にかシンパシイのようなものを覚え始めてしまうのは、実際のヒグマに身を以て接触したことのない者の浅はかさなのでしょうが、しかし、原生林の本来の住民はヒグマの方で、人間の方が侵略者だったというのは争えぬ事実です。人間としてはできるだけ平和的共存を図り、ヒグマが身近にうろうろしていも、実害が無い限りほうっておく、という牧歌的なおおらかさがこの書のなかでも描かれていますが、なまじっか巨大で強力無比な獣だけに、共存にも限度があり、どうしても接触には殺し合いがつきものになってしまう悲しさがあります。
その悲しさが、決して、「ヒグマが北海道から絶滅した」という悲しさには発展しないことを、私は祈って止まない。
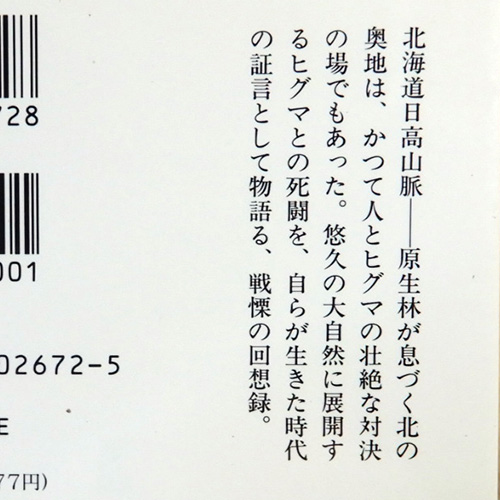
今野保『羆吼ゆる山』
追記。
絶滅といえば。
かつて北海道に多数生息していたエゾオオカミは、1900年頃に絶滅したと公式には考えられている。
本州~九州に生息していたニホンオオカミも、そのわずか数年後に絶滅したとされている。
が、その後も、エゾオオカミ・ニホンオオカミともに、生存説が各地で長くささやかれていた。
この本でもしかり。
わずか一か所、それもほんの数行触れられているだけだが、エゾオオカミかもしれない動物がうわさされる。
そして、私や友達がいつも不気味に思っていた獣に、山犬と呼ばれ、集団で動き回る体の大きな犬たちがいた。母が、「昔から北海道に生息し、絶滅したはずのエゾオオカミにそっくりだ」と語っていたが、それは体型から灰褐色の毛色に至るまでエゾオオカミに良く似ていた、と思われる。
(p.16)
もしこの動物がエゾオオカミだったなら・・・
もし日本政府が保護政策をとっていたならば・・・
どうにもこうにも、残念でならない。
(2012.4.13.)
※著作権法に配慮し、本の中見の画像はあえてボカシをいれております。ご了承ください。
『羆吼ゆる山』
- 著:今野保(こんの たもつ)
- 出版社:中央公論社 中公文庫
- 発行:1996年
- NDC:914.6(日本文学)随筆、エッセイ
- ISBN:4122026725 9784122026728
- 323ページ
- 登場ニャン物:-
- 登場動物:ヒグマ、他




