デカルト『方法序説』

「動物機械論」=動物に魂や精神はあるのか?それとも、ただの自動機械か?
今回は、あの超有名な哲学者、デカルトの著。
「え?ここは猫本紹介コンテンツでは?なぜデカルト?」と思われる人も多いかもしれない。が、動物の権利や解放について、少しでも調べた事のある人なら、「あの悪名高き《動物機械論》か!(怒)」と思い当たるだろう。そう、動物愛護の世界ではデカルトは悪魔の使者みたいな存在。多くの動物達を苦しめてきた張本人みたいな扱いだ。
ルネ・デカルトは1596年にフランスで生まれた。8年間人文学とスコラ学を、さらに1年間医学と法学を学んだ後、志願士官としてオランダに赴き、科学者ベークマンと知り合い、数学や物理の共同研究をおこなう。その後ドイツ駐屯中に炉部屋で思索を重ねて、一生を哲学にささげる決心をした。軍籍を離れた後は、各種科学実験を行う傍ら、科学論文や哲学書を発表。1650年、招かれたスウェーデンにて客死。近代哲学の祖とされ、長らく崇められてきた人物である。
(前略)これらの多くは近代を貫く諸原理となっていく。二〇世紀の今日にいたるまで、その基礎構造は、われわれの学問の基本的な枠組みをなしているともいえる。考えるわたし、近代の意識や理性の原型、精神と物質(身体)、あるいは主体と客体の二元論、数学をモデルとする方法、自然研究の発展・・・。デカルト主義は近代合理思想の中心原理となっていった。
「解説」ISBN:9784003361313 page135
西洋ではもちろん、文明開化後の日本でも、デカルトはもてはやされた。学生歌の「デカンショ節」は「カント・デカルト・ショーペンハウエル」から来ているとの説が強いし、インテリ青年たちは、外国語を読めても読めなくても、デカルト等の原書を小脇にかかえて歩くのが当時の最新ファッションだった。
しかし現在、デカルト的近代思想に対する批判が増えてきたのも事実だ。中でも多くの人々が反発するのが、「動物機械論」。私自身も、デカルトその人はすごい偉人と尊敬するけど、この動物機械論だけは許せない。というか、それ以前に、理解できない。何故デカルトほどの頭脳の持ち主が、こんなバカげた論を展開したのか?本当に彼は本気でこんな愚論を信じていたのか?ウッソでしょ、って感じ。
おそらく、・・・と、これはあくまで私の想像なのだが、・・・おそらく、この「動物機械論」は、当時の社会全般の漠然とした認識だったのだろう。それをデカルトがうまく言葉でまとめあげてしまった。それが人間社会にとってあまりに都合の良い理論だったので、・・・こんなに都合のよい理論はなかったので、当時の人々、中でも知識人達が、大歓迎した。その内容が真実かどうかは関係無く、ただただ「都合がよかった」から受け入れられたのではないか、と。そう、まさに儒教が支配者層に歓迎された理由と同じく受け入れ側の「都合」だけで。(思想としては老荘思想の方が深いですよね?でも人民に老荘を究められたら支配者層はおおいに困る。)
デカルトの「動物機械論」こそ、動物達を家畜として情け容赦なく扱うために最も都合のよい理論だったのだ。なにしろ、彼らに精神はないのだから。理性も魂もないのだから。ただの「機械」なのだから。
デカルトの「動物機械論」
以下、引用文が非常に長くなってしまうのだが、「動物機械論」を理解する上で重要なので許していただきたい。もちろん、デカルトの論を本当に理解するにはこれでも全然足りなく、「第5章」全文を書き出しても足らないくらいなのだが。(翻訳された谷川多佳子様、引用させてください。皆様も『方法序説』もし未読であればぜひお読みください。薄い本ですから多分すぐ読めます。「アニマル・ライト」がやっと一部の日本人に認識され始めた令和の今だからこそ読み返したい書物であると言えます。)
デカルトはまず、肉体の仕組みを説明する。心臓はどのように動くか、血液はどのように巡るか。彼の医学知識の限りをつくして懇切丁寧に説明する。そして、それらすべてがいかに自動的に行われているかを力説する。その動く様子は、まるで我々人間がつくる自動機械=オートマットとそっくりだ、と。いや、似ているどころか、まったく同じではないか、と。
そう、身体が動く仕組みは、「機械」そのもの。全知全能の神が作りたもうた精巧な機械なのだ、と結論付けるのである。
(前略)各動物の体内には骨、筋肉、神経、動脈、その他あらゆる部分が無数にあり、それに比べれば実にわずかの部品しか遣わずに、人間の巧知がどれほど多種多様のオートマットを作りうるかを知って、この人体を、神の手によって作られ、人間が発明できるどんな機械よりも、比類なく整えられ、みごとな運動を自らなしうる一つの機械とみなすであろう。
ISBN:9784003361313 page74
デカルトは続ける。人の体(肉体部分)は機械と同じ。もし人の器官と、それとそっくり同じ他の動物の器官とを入れかえてしまっても、我々は見分けさえつかないだろう、と。
(前略)もしそういう機械があって、サルか何か理性を持たないほかの動物の器官と形状を持つとすれば、この機械がそうした動物とどんな点でも同じ性質のものでないと見分ける何の手段も、われわれにはあるまい。
ISBN:9784003361313 page74-75
しかし、人間と機械はふたつの点で違なるという。第一は、機械は決して、自分で考えて自分のことばで話すことはできないということ。第二は、機械はどれほど精巧かつ巧妙に作られようと、そう設計製造されているからそう動くだけであって、人間のように己の理性で判断して動いているわけではない、ということ。
これに対して、われわれの身体に似ていて、実際上可能なかぎりわれわれの行動を真似る機械があるとしても、だからといってそれが本当の人間ではない、と見分けるきわめて確実な二つの手段が、やはりわれわれにはあるだろう。その第一は、これらの機械が、われわれが自分の思考を他人に表明するためにするように、ことばを使うことも、ほかの記号を組み合わせて使うことも、けっしてできないだろうということだ。機械がことばを発するように、しかも器官のなかに何らかの変化をひき起こす身体作用に応じて、いくつかのことばを出すように作られていることは十分考えられる。たとえば、機械のどこかに触れると、何を言いたいのですかと質問し、ほかの所に触れると、痛いと叫ぶとか、それと似たようなことだ。けれども、目の前で話されるすべてのことの意味に応じて返答するために、ことばをいろいろに配列することは、人間ならどんなに愚かな者でもできるが、機械にできるとは考えられないのである。第二は、このような機械が多くのことをわれわれのだれとも同じように、あるいはおそらくだれよりもうまくやるとしても、あるほかの点でどうしてもなしえないことがあり、それによって、機械は認識することによって動くのではなく、ただその諸器官の配置によって動くだけであるのが分かることである。
ISBN:9784003361313 page75-76
人間と違って、機械は理性で状況判断することはできない。だから何をさせるにしても、そうするように、ひとつひとつ設計+部品配置しておく必要がある。けれども、どこで何がおころうとすべての事象にも対応できるように、いちいち個別設計したものをひとつの機械に全部いれておく、なんてことは実際上不可能である。
というのは、理性がどんなことに出合っても役立ちうる普遍的な道具であるのに対して、これらの諸器官は個々の行為のために、それぞれ何か個別的な配置を必要とするからだ。したがって、生のありとあらゆる場合に応じて、理性がわれわれを動かすのと同じやり方で、一つの機械のなかに、諸器官が十分多様に具わってその機械を動かすということは、実際的に不可能なことになる。
ISBN:9784003361313 page76
と、以上までは現代にも通じる「人間対機械論」だ。”ChatGPT”のような人工知能が登場した現代でさえ、人間はふつうに、機械と人を区別して暮らしている。ロボットをぶったたくと「痛い!」と叫ぶようプログラミングすることは今の時代では簡単だが、機械が、人間が痛みを感じるのと同じ感覚で痛みを感じているとは、誰も考えない。ましてデカルトの時代では、機械といえば、ガチャコン、ガチャコンと歯車で動くようなものだったろう。機械と人間の違いを説明するのに、わざわざ哲学者が出てくるまでもない。
もちろん、デカルトの狙いは機械そのものではなかった。機械の説明をすることで、強引に「動物=機械」論に持っていこうとしていたのである。
デカルトは、つぎのように続ける。人間と動物の違いも同じことだ。人間ならどれほど愚かなものでも、自分でことばを組み合わせて話しができるが、動物には決してそれができない。器官(声帯)を欠いているからではない、オウムのような鳥もいるじゃないか。なのに話せないのは、機械同様、動物に理性や魂というものがないからだ。すこしでも理性があるなら、声帯もあるのだから話せるはずだ。話せないという事実こそが、動物に理性がまったく欠如していることの何よりもの証拠である、と。
さて、この同じ二つの手段によって、人間と動物の違いも知ることができる。人間ならばどんなに愚かで頭がわるくても、狂人でさえもその例外でなく、いろいろなことばを集めて配列し、それでひと続きの話を組み立てて自分の考えを伝えることができるが、反対に、他の動物には、どんなに完全でどんなに生まれつき素質がよくても、同じことができるものはない。これはきわめて注目に値することだ。それは動物が器官を欠いていることによるのではない。なぜなら、見て分かるとおり、カササギやオウムはわれわれのように音声を発することはできても、われわれのように話すこと、つまり自分が言うことは自分が考えていることであるのを明示しながら話すことはできないからである。一方人間は、生まれつき耳も聞こえず口もきけず、ほかの人に話をするのに役立っている器官が、動物と同じか動物以上に欠けていても、ふつう何かの記号を自分たちで発明し、その記号によって、つね日頃いっしょにいてその言語を習いおぼえるゆとりのある人たちに自分たちのことを理解させるのである。そしてこのことは、動物たちの理性が人間よりも少ないということだけでなく、動物たちには理性が無いことを示している。というのも、話すことができるためには、ごくわずかなの理性しか必要ないことは明らかだからだ。同じ種の動物でも、人間どうしのあいだと同様に不平等が認められるし、あるものはほかのものにくらべて訓練されやすいということがあるだけに、その種のなかで最も完全なサルやオウムが、最も愚かな子供あるいは少なくとも頭に障害のある子供にさえ、この点でかなわないというのは、動物の魂がわれわれ人間の魂とまったく異なるものだとしないかぎり、とても信じられないことである。
ISBN:9784003361313 page76-77
「動作」に関しては、機械も動物も「模倣可能」なものであるから、考慮の必要はない。時計は歯車とゼンマイだけで動くし、人間より正確に時を刻むではないか。問題は「ことば」だ。人語を話せない動物に精神はない!
なお、ことばと自然の動作を混同してはならない。自然の動作は情念をあらわし、機械によっても動物によっても模倣されうるのである。またある古代人たちが考えたように、動物はことばを話すけれども、われわれがそのことばを理解しない、と考えてはならない。なぜなら、もしそれが本当なら、動物たちはわれわれの器官に似たたくさんの器官をもっているのだから、その仲間にたいしてと同様われわれにも、話を通じ合うことができるだろうから。また次のようなたいへん注目すべきこともある。多くの動物たちはある種の行動ではわれわれ人間以上の巧みさを示すが、その同じ動物がほかの多くの行動ではまったくそれを示さないことが認められる。したがって、動物のほうがわれわれよりもやり方がうまくても、動物に精神があるという証明にはならない。というのも、この理屈でいくと、動物たちはわれわれのだれよりも精神がたくさんあり、どんなことでもわれわれより巧みにやれることになってしまうからだ。そうではなくて、むしろ次のことを証明しているのである。動物たちには精神がなくて、自然が動物たちのうちで諸器官の配置にしたがって動いているのだ。たとえば、歯車とゼンマイだけで組み立てられている時計が、われわれが賢慮を尽くしても及ばぬ正確さで、時を教え、時間を計ることができるのは知られていることだ。
ISBN:9784003361313 page77-78
と・・・!
なーんか、あまりにひどい理論で、もう笑っちゃうしかないんですけれど?!
まず、何故「似ている」というだけで、その器官が人間とまったく同じように作動可能と考える?例えば、フルートもクラリネットもオーボエも、音がでる仕組みはそっくりである。トランペットやホルンやスーザフォン、またオカリナや尺八等も、筒の中を空気が通って、という基本構造は同じだ。にもかかわらず、フルートとクラリネットの音は違うし、ましてフルートにスーザフォンの音は絶対に出せない。出せないが、どちらもみごとな音楽を奏でることはできる。
動物たちが、人間のものに似た咽や舌を持っているからと言って、どうして彼らが人間と同じ発音で人語を話せるはずだと決めつけられるのだろう?大きさも構造も人間のものとは少しずつ違っているのだから、同じ発音ができなくて当然ではないか。逆に、人間はヒバリのようには鳴けないし、猫のように咽をならすこともできない。似た器官を持っているのに、しかも人間の方が(デカルトによれば)動物より優れているはずのに、人間にゴロゴロ咽はならせない。それと同じことではないか?
だいたい、なぜ動物の側が人の真似をする必要があると考えるのか?人間の方が優れているのであれば、人間の側が動物語を理解するようもっと務めるべきではないのか。人間が、猫のように咽を鳴らせられないことを棚に置いて、猫が、人語を話せないことを批判するとは、科学者としてどうなんだと思わずにいられない。デカルトは哲学者であると同時に、科学論文を発表するような科学者でもあったはずなのだから。
実際のところ、多くの(多分すべての)動物たちが、彼らの方法でちゃんと”会話”していることが明らかにされつつある。動物だけでない、植物同士も交信しあっているらしい。その事実を知ったらデカルトはどう反論するだろうか。
それにそもそもデカルト自身が言っているではないか。「生のありとあらゆる場合に応じて、理性がわれわれを動かすのと同じやり方で、一つの機械のなかに、諸器官が十分多様に具わってその機械を動かすということは、実際的に不可能なことになる」と。ひとつの”機械”に全部を突っ込むのが”不可能”であるならば、なぜ、動物達は”体というひとつの機械の中”に、人間そっくりな諸器官(=機械的仕組み)を、しかし人間と違って理性は持たずに、全て持つことが可能だといえるのか?17世紀にコンピューターは無く、プログラミングという概念もなかったはずだ。機械はすべて、歯車やゼンマイや蒸気その他で動かしていた時代である。無機と有機の違いがあるとはいえ、ネズミや蚊のような小さな体に、どうすればそれほどの機能をブッ込めるというのか。
デカルトは科学の実験をしたり数学を研究したりと、理性的で科学的だったと自認しているようだが、私にいわせれば、少なくとも動物観察に関しては、およそ非科学的な頭脳の持ち主だったとしか思えない。でなければ、ただの詭弁家だ。そういえばデカルト自身、『方法序説』の中でこんなことも言っていたっけ。
哲学はどんなことについても、もっともらしく語り、学識の劣る人に自分を称賛させる手だてを授ける。
ISBN:9784003361313 page13
けれども残念なことに、デカルトの「動物機械論」は白人キリスト教社会に歓迎されてしまった。前述の通り、とても都合がよかったからだ。
たとえば。現代ならば、スマートフォンという手のひらサイズの機械が、どれほど多くの事をできるか、我々は知っている。しかし、もしそのスマホを床に落とした場合、我々は壊れたかどうかは気にするけれど、そのスマホに「落下恐怖という精神的苦痛」を与えたかと気にする人はいない。スマホは決してそのような精神的苦痛を感じることはないと知っているからだ。
デカルトは、動物達はそのスマホと同じだと言ったのである。たとえば、重過ぎる荷を積んだ馬車を馬に引かせて、その馬が倒れたとしても、御者が気にすべきはその馬が機能停止(死亡)したかどうかだけということになる。鞭でひっぱたいてまた歩き出すようなら、何の問題もない。馬の苦痛を心配する必要はない。なぜなら馬は自動機械にすぎないのだから。同じように、生きた鶏を運ぶ時、箱にぎゅうぎゅうに押し重ねて押し込んで、長時間そのままにしておいても、何も気にすることはない。なぜなら鶏は自動機械なのだから。そう、我々がスマホを箱に重ねてギッシリ積み上げても何とも思わないように。そして、もし馬や鶏が泣き叫んだとしても、それも無視してかまわない。その機械はそのような場面ではそのような声を出すように設計されているだけなのだ。自動機械には精神も理性もない。
この「動物機械論」という考え方は、つい最近まで行われていた。否、家畜については、今現在もなお頑迷に行われ続けている。でなければどうして鶏たちを狭いバタリーケージに閉じ込めることができるのか。高度な知能を持つブタたちを妊娠ストールに押し込めて平気でいられるのか。動物には精神も理性も感情も無いとでも決めつけないかぎり、あのような虐待を続けられるはずがない。また、ワンちゃん大好き~といいながら、鼻をつぶしたり脚を短くしたりと犬体改造し、さらに尾や耳を切り取り(断尾・断耳)、強制レイプし、麻酔無しで腹を切って子犬を取り出し、商品にならない子犬を処分する、なぜそんなことができるのか。デカルト的動物観のままではないか。日本の法律では今でも動物=モノ扱いだし。
「動物機械論」は残念ながら17世紀の廃墟ではないのだ。17世紀に建立され、ところどころ補修されながら、今なお現役で堂々使用されている大聖堂なのだ。
しかしデカルトにとって皮肉なことに、科学が発達するほど、人間と他の動物たちとの差異の小ささが次々と証明されつつある。当然だ。なぜなら人間だって動物の一種にすぎないのだから。
その一方で、人口が増え人間活動が活発になるほど、動物とくに家畜たちの苦悩は増大傾向にある。この膨大な人間たちの底知れぬ欲を満たすために、動物たちは日々搾取されつづけている。その悲惨さはデカルトの17世紀をしのぐほどだ。
人間と、人間以外の動物たちが対等になる日は、いったい、いつ来るのだろうか?
それとも・・・そんな夢のような日は、人類が滅びない限り、永遠に来ないのだろうか・・・・・・
附(長文)
いくらデカルトでも、動物の体の中にゼンマイや歯車があると考えていたわけではない。肉体や感情が動く仕組みについては、『情念論』で詳しく解説されている。その内容をごく大雑把に、単純化して説明すると;
- 身体を動かすのは、血管の中を流れる血液と、神経管の中を流れる動物精気(精気)の働きによる。それらの流量・濃度・方向・熱量等によりあらゆる内臓や筋肉動作のみならず、感覚器官(感情)も動く。
- 動物精気とは、脳内で血液中から分離された物体で、微小で敏速に動き、いかなる場所にもとどまらず、脳室内部の孔を通って、神経へ、さらに筋肉へと流れることで、身体を動かす物のことである。
- すべての種類の思考は精神に属する。精神と動作は別に動く。そして、身体は精神の下にあるものである。
- 精神は人間だけが持つ。
- 動物は精気や腺の運動すべてを備えているが、理性を持たず、おそらく何の思考も持たない。
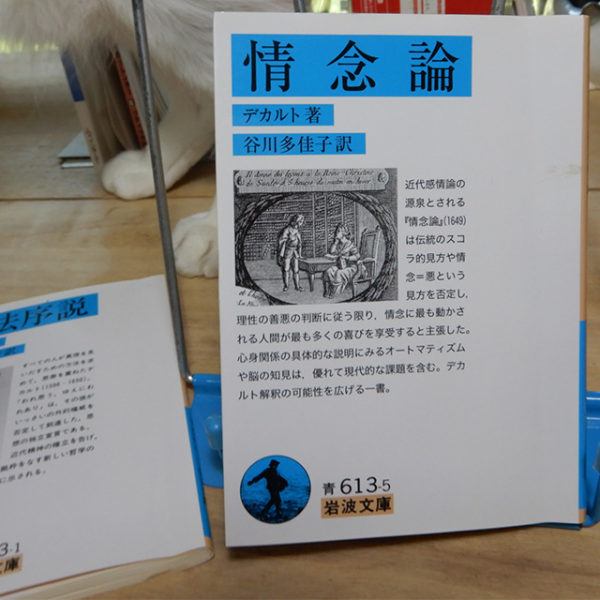
つまりデカルトによれば、動物も、わたしたち人間のうちに情念を引き起こす精気や腺の運動すべてを備えているものの、わたしたちの場合のように「情念」を維持し強める役をすることはなく、「神経や筋肉の運動」を維持し強める役を果すだけである。そんな「理性を欠いた動物」でも、訓練などの工夫で脳の運動を変える事はできる。犬などがよく訓練できるのはそのためだ。しかしその犬はどれほど賢く見えても、人間が精気の流れを変えただけ、つまり、脳内コードを書き換えただけであり、犬自身の理性で判断しているわけではない、というわけだ。
また、こうも言っている。
苦痛とよばれる感覚はつねに、神経を害するほどの激しい何らかの作用から生じる。苦痛の感覚は、その激しい作用から身体が受ける損傷と、その作用に身体が抵抗できなかった弱さとを、精神に示すために自然が設けたものだ。
『情念論』 ISBN:9784003361351 page82-3
ということは、精神を持たない動物は苦痛を感じることもない、ということになる!!
さらに、こんなことも。
最も高邁で最も強い精神をもつ人たち(中略)も、他の人たちの弱さを見、その嘆きを聞くとき、同情心を持たなくはない。(中略)しかし、この憐みに含まれる悲しみは、辛いものではない。その悲しみは、舞台で演じられるいたましい展開を見たときに引き起こされるのと同様、精神の内面よりも外面、感覚のうちにある。精神はそのとき他方で、苦悩する人々に同情することで自分のなすべきことを果していると考える満足をもつ。
『情念論』 ISBN:9784003361351 page160
他人の嘆きを見ても、「最も高邁」なひとたちは辛いとは感じないどころか、悲劇を観劇するとき同様の心理状態で、むしろ満足感を覚える?ということ・・・??
同じ人間同士に対しても、高邁な精神の持ち主は「我が身のように悲しむ」ことはないというなら、まして相手が動物であれば・・・どれほど動物が悲鳴を上げようと、苦痛にのたうち回ってる「かのように」見えようと、全然同情する必要なんかない。あるわけない!動物たちに感情移入するなんて、高邁な精神を持つ人間のすることじゃないのだから!・・・って、こと????×∞
(nekohonのぼやきです)
デカルトは、人間のことを、絶対的に優れた存在、神のすぐ横に立つほぼ神的存在、と考えたかったに違いない。ところが、多少は医学を勉強し、そのときに解剖実験を行ったかもしれず。そしてブタなどの動物の体と、ヒトの体の仕組みが、あまりに似ていることに・・・デカルト自身の言葉によれば「見分けがつかないほどそっくり」なことに・・・驚愕し周章狼狽したのかもしれない。
「いやいや、そんなハズはない!人間様の方がはるかにすぐれている!人間様とブタが同じワケない、ぜったいに!」
で、思いついたのが動物機械論?!
「人間様には動物には決して持てない《精神》というものがあるんだもんね!そうさ、えらいんだもんね!へへへっ」
ってな感じだったのでしょうか(ため息)。
もしデカルトが逆に、ヒトも他の動物達となんらかわりはない、どちらも自動機械のようなものなのだからと言ったのなら、私のデカルト評価は爆上がりしていたのですが。
※著作権法に配慮し、本の中見の画像はあえてボカシをいれております。ご了承ください。

著者について
ルネ・デカルト Rene Descartes
1596-1650。フランスのトゥーレーヌ州ラ・エ(現デカルト)に生まれ。階層的には法服貴族。著作に、『世界論』、『方法序説』、『省察』、『哲学原理』、『情念論』など。
(著者プロフィールは本著からの抜粋です。)
『方法序説』
- 著:ルネ・デカルト Rene Descartes
- 訳:谷川多佳子(たにがわ たかこ)
- 出版社:岩波書店
- 発行:1997年
- NDC:135.23(哲学)
- ISBN:9784003361313
- 137ページ
- 原書:”Discours de la methode” 1637
- 登場ニャン物:-
- 登場動物:-



