メルヴィル『白鯨』

コーヒーで有名な「スターバック」の由来となった本。
最近、「捕鯨」という文字をよく目にする。2014年3月31日、オランダ・ハーグの国際司法裁判所(ICJ)で、日本が敗訴したからだ。
日本は、南極海での「調査捕鯨」を、「実質的な商業捕鯨であり、国際条約に違反する」と訴えられていた。提訴したのはオーストラリア。それを受けた国際司法裁判所は、日本の「調査捕鯨」は科学的ではないと判断、南極海での第2期調査捕鯨について中止命令を下した。その結果、日本の水産庁も、第2期調査捕鯨の中止を発表した。
捕鯨推進派の人々は、クジラを食べるのは日本の伝統的食文化だ、守らなくちゃならないと主張する。しかしほとんどの日本人は、今の時代、クジラを食べる必要性は無いと考えているのではないだろうか。
私も、もう捕鯨は必要ないだろうと考える一人だ。昔の日本人にとって、クジラが重要な存在だったことは理解できる。でも、昔の手漕ぎ船での手投げ銛ならいざしれず。現代の、遠海まで大型船で出かけて、レーダーでクジラを探知し、火薬で銛をぶっ放すというような捕鯨は、まず感情的な反発を覚えざるを得ない。そして理性的にも、・・・日本人のクジラ肉離れによる消費低迷で冷凍クジラ肉在庫が約4千トンにも積みあがっているとか、財団法人日本鯨類研究所は大赤字でその借金返済に東日本大震災復興予算から23億円もの税金が流入されたなどを、知ってしまった以上、捕鯨に賛成する気には、もう、なれないのだ。
なんて考えていたら、突然、メルヴィルの『白鯨』をまだ読んでいないことを思い出した。
言わずと知れた世界的名著。世界各国で翻訳され、翻案され、何度も映画化された。それらの映画や子供本を見ていたから、なんとなく知った気になっていたが、良く考えれば原作をまだ読んでいない。本はある。昔買ったまま、もう20年も忘れていた。
さっそく本棚から、新潮文庫「白鯨 上・下」を引っ張り出し、積もり積もったホコリを払って、いざ、古き名作を読まん!
お、おもしろく・・・・ない!(汗)
ぐったら、ぐったらと、長々しい文章が続く。ああ、私の大いなる勘違いだ!映画や絵本で見たドラマチックなラストシーンだけを、やたら鮮明に覚えていた、だから『白鯨』は全編が、手に汗握る大アドベンチャーだと、今の今まで思い込んでいた。それが間違いのもと。
全然「手に汗握る大アドベンチャーの連続」なんかじゃなかった。
なんといえばよいのか。「ごった煮本」とでも言えばよいのか。
本は、「文献抄」から始まる。
「神巨(おほい)なる鯨(うを)を創造(つく)りたまへり」創世記(聖書)
等々、古今東西の様々な文献から引用された、様々な文章の羅列が25ページ分。
その後、やっと小説が始まるのだが。
大時代的な、大仰な文章。登場人物は全員、一癖も二癖もある奇人ばかり。詳細な描写、しかし詳細な分、進展がいかにも遅い。遅いどころか、頻繁に立ち止まる、寄り道もする。クジラという生物について、あるいは、捕鯨や船についての、長大なウンチクが大量に挿入されているのである。小説というよりは資料館だ。読んでいるうちに、誰もが疑問を感じるだろう。メルヴィルは本当はクジラと捕鯨について書きたかっただけではないか、しかしクジラ学オンリーでは本にしてもらえぬから、仕方なく「小説」も織り込んだだけではないか、と。
そう、主体は「小説」ではなく「クジラ」。クジラの虜となっているのは、船長エイハブではなく、著者メルヴィルの方だ、明らかに!
語り手はイシュメールという男だが、主人公は船長エイハブの方だろう。エイハブは、モービィ・ディックと呼ばれる白くて巨大なマッコウクジラに、片足をもがれた。以来、白鯨への復讐心で燃えたぎっている。復讐だけのために生きている狂人のようなものだ。陸には妻も子もいるのにね。「悪の象徴的存在」と評さるのも仕方あるまい。
船長が「悪」なら、「善」は一等航海士のスターバックである。スターバックは冷静で良識的、狂った船長をたしなめることができる(少なくともたしなめようとする)唯一の男でもある。
「物いわぬ畜生相手の仇討!」スターバックも大声で「鯨はただ盲目な衝動からあなたを噛んだにすぎんのです。気違い沙汰だ!畜生に恨みを持つなんて、エイハブ船長、とく神の仕業ですぞ!」
(上巻p.273)
ところで「スタバのコーヒー」として日本でもすっかり有名になった「スターバックス」という社名は、この一等航海士から取られたらしい。
もうひとり、印象的な人物として、クィークェグの名ははずせない。巨漢の食人種で異教徒の「蛮族」と表現されているが、語り手イシュメールの親友でもある。勇敢無比な銛撃ち。肉体的に優れているだけでなく、知能もすこぶる高そうだ。否、知能が高いとは本には一言も書いていない、なにしろメルヴィルの時代(1850年頃)は徹底した白人至上主義だったようで、たとえば「白」という色を形容するにあたっても
・・・この色の卓越性は人類そのものにおいてもあてはまり、白色人種に対して、あらゆる薄汚れた色の種族の上に立つ概念上の優位を与えているし・・・
(上巻p.314)
なんて書いてあるくらいで、蛮族の知能が白人種より優れているなんて、決して書きやしない。が、彼の、様々な場面で見せる理解力や応用力は、「この船で一番賢いのでは」と、私には思え、私の目にはもっとも魅力的な人物と映るのである。
クィークェグと対照的に、まったく魅力ないのが、語り手のイシュメール。この男、個性というほどの個性もなし、船の上でもいったい何をしているのかわからない。なぜメルヴィルは、この長編を書くにあたって、わざわざイシュメールの口から語らせたのだろう?イシュメールという第3者がいるために、各登場人物は外側からしか描けないし、またイシュメール自身が実質何もしていないがために、どんなシーンも結局は傍観でしかない、私が「面白くない」と感じたのも、おそらくはそこだ。これほど個性豊かな人間がそろっているのに、そしてこれほど緊迫した人間関係が描かれているのに、なんとなくもどかしいのは、多分視点が人間の低さに保たれているからだ。小説家とは、神の視点から人間観察をできる稀有な職業である。イシュメールの存在意義って何なのだろう不要じゃん、と思いながら読み進めて、しかし最後の最後に、ハッとする。
1頭の白鯨と、男たち30人の死闘は、この1000ページ近い小説の、最後の数ページしか占めない。1000ページも引っ張ってきて、最後の40ページでやっと白鯨にまみえ、追いすがり、突進して、エイハブ船長はわずか1行で完敗する。船も沈む。男たちも沈む。サメが集まる。残骸だけが残る。
そしてその瞬間だけ、メルヴィルの視点が、いきなり神の高みにあがるのだ。
が、たちまち、また地上に落ちる。イシュメールだけが、あの「目」以外は無能とさえ思われたイシュメールだけが、偶然生き延び、救われるのだ。そして、救われた瞬間、視線もまた人間レベルに落ちるのだ。
ああ、これだったのか、と、私は膝を打つ。
白鯨こそ、神なのだ。神を追う人間の愚かしさをあざ笑う小説だったのだ。
これから『白鯨』を読まれる方は、決して冒険小説としては読まないでください。鯨や捕鯨業の資料書、あるいは神話・バイブルを読むつもりで、ハラハラ・ドキドキは期待せずに読んでください。そうすればきっと楽しめます。ハラハラ・ドキドキもきっとできます。
読み終えて思ったこと。名著といわれる本は、やはり、名著だった。つぎに再読するときは、今回よりずっと楽しめそうだ。
(2014.4.27.)
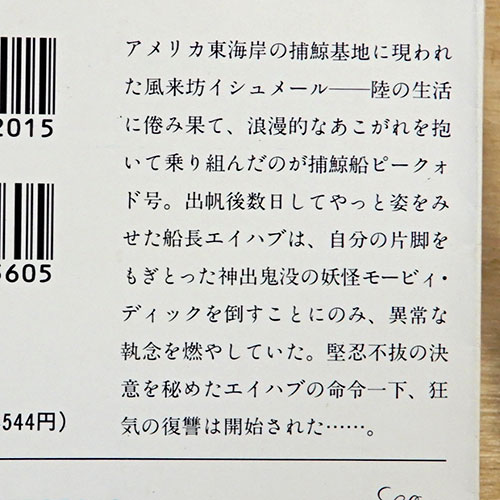
メルヴィル『白鯨』上
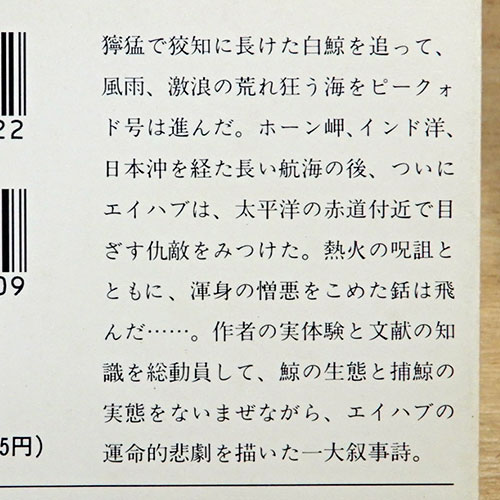
メルヴィル『白鯨』下
※著作権法に配慮し、本の中見の画像はあえてボカシをいれております。ご了承ください。
『白鯨』
- 著:ハーマン・メルヴィル Herman Melville
- 訳:田中西二郎
- 出版社:新潮文庫 上・下
- 発行:1952初版発行
- NDC:933.6 アメリカ 長編小説
- ISBN : (上)4102032010 9784102032015; (下)4102032029 9784102032022
- 502ページ、492ページ
- 原書: ”Moby-Dick; or, the Whale” c1851
- 登場ニャン物: -
- 登場動物:モービィ・ディック(マッコウクジラ)



