リリアン・J・ブラウン『猫はシェイクスピアを知っている』

本棚からシェイクスピアの本をつぎつぎと落とすココ。
古アパートなどで庶民的な生活を送ってきていたクィララン。
莫大な遺産を受け取って、豪華なK屋敷に住むようになったが、どうも居心地が悪い。
離れのガレージの2階を自分好みに作り替えて、ようやく落ち着けた。
元は従業員部屋だった場所である。
一方、家政婦のコブ夫人の部屋は、母屋のフレンチ・スイートである。
贅の限りを尽くした、アンティーク家具の大部屋。
まるで主従逆転で、他人から見ればおかしいだろうけど、当人たちにとっては、この状態こそハッピー。
そして、コブ夫人がハッピーになっている要因がもうひとつあった。
恋だ。
交際相手は、ハーブ・ハックポールだった。
結婚まで視野にいれてた。
が、ハーブは町の嫌われ者だった。
クィラランもこの男がどうも気にくわない。
もしコブ夫人が結婚してしまったら、優秀な家政婦を失うことになるという、自己本位の理由だけではなかった。
どうしても好きになれないのである。
しかし、アイリス・コブが、少女のようにいそいそとデートに飛び出す様子を見せつけられては、反対もできなかった。
コブ夫人は、過去に夫を2回も亡くすという不運に見舞われている。
でありながら、夫と呼べる存在を切実に必要とするタイプの女性でもあった。
彼女には幸せになってほしかった。
一方、ココは新しい悪戯に夢中だった。
本棚にのぼって、貴重な革表紙の本を引き出しては床に落とす。
なぜかシェイクスピアの戯曲ばかりだった。
テンペスト、ハムレット、ヘンリー八世、またハムレット、またテンペスト。
クィラランは首をひねる。
これは、単なる遊びか?
それとも、何かを伝えようとしているのか?
なんぜ、あのココのすることなのだから・・・。
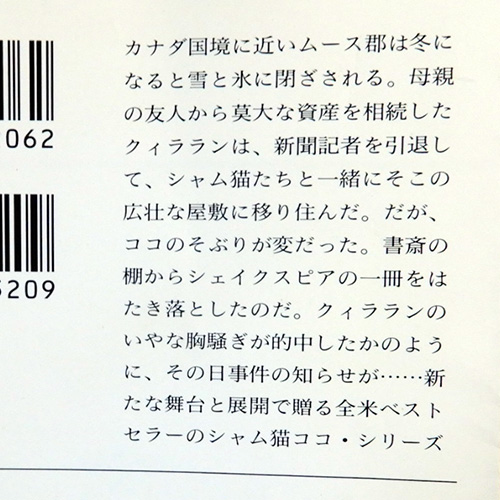
ブラウン『猫はシェイクスピアを知っている』
*****
細かい描写、子細な人物像、いつも通り丁寧に始まっているのですが、なんだろう?最後の方はちょっと端折ったような、ちょっと雑?な印象をうけました。
というのも、たとえば終盤に近いところで、自動車事故で2人の人間が死にます。
犠牲者のひとりは、クィラランが考えたビジネスのために、クィラランが当地に呼んだ南部の知人でした。
なのに、クィラランは彼には関心を示さず、お悔やみひとついいません。
また、コブ夫人の悲劇についても、なんかあまりにあっけないような。
もう少し言葉があってもいいんじゃないの?と、日本人の私はつい感じてしまいます。
もしこれが、テンポよくどんどん話を進めていくタイプの作家さんであれば、上記のことなど、気にならないでしょう。
でもブラウン氏は、ときには回りくどく感じるほどなのです。
なぜノイトンの事故死にクィラランが無反応なの?とか、ちょっと不自然に思ってしまいました。
締め切りに追われていたとか、あるいは枚数制限を超えそうだったとか、なにかはしょる理由があったのかなあ・・・?
でも、最後はさすがブラウン氏でした。
クィラランは、最後の現場で、猫たちのことだけを心配します。
猫たちの安全しか考えていません。
高価なアンティークとか、高額の証券とか、その他いろいろあったに違いないもの、さらに、豪壮な屋敷そのものさえ、まったく眼中にありません。
ひたすらに猫たちを心配し、猫たちを案じて狂ったようになります。
人が死ぬより、知人が不幸に会うより、ココとヤムヤムが大切な、クイラランなのでした。
※著作権法に配慮し、本の中見の画像はあえてボカシをいれております。ご了承ください。
『猫はシェイクスピアを知っている』
『猫は・・・』シャム猫ココシリーズ
- 著:リリアン・J・ブラウン Lilian Jackson Braun
- 訳:羽田詩津子(はた しづこ)
- 出版社:早川書房 ハヤカワ文庫
- 発行:1992年
- NDC:933(英文学)アメリカ長編小説
- ISBN:4150772061 9784150772062
- 287ページ
- 原書:”The Cat Who Knew Shakespeare” c1988
- 登場ニャン物:ココ(カウ・コウ=クン)、ヤムヤム、ウィリアム・アレン
- 登場動物:-



